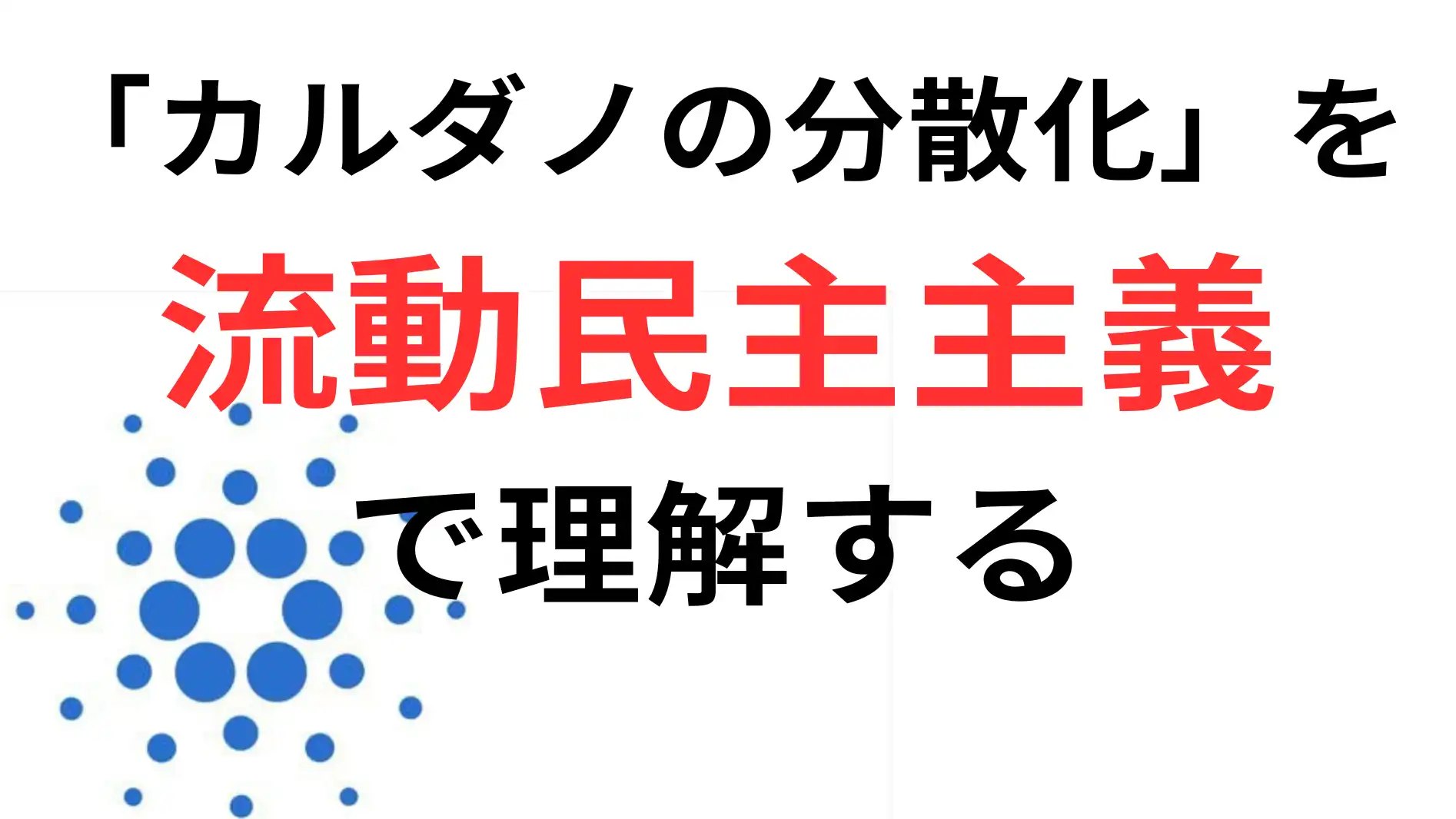この投票では、「SPOの投票を最終結果とする形式で、コミュニティの意思決定をすることに賛成か?」という問いが提示され、これをADAホルダーの皆さんがdApps形式で投票する、という方法がとられています。
CIP-1694って、そもそも何なの?
この「CIP-1694」は、カルダノの分散化に向けた最終フェーズに向けた「Cardano Improvement Proposal(設計案)」の一つです。
現在、カルダノのブロックチェーンは「ブロック生成」と「バージョンアップ」に関しては、世界中の3000を超えるステークプールが行っており、ブロックチェーン運営については分散化が完了しています。
一方、ブロックチェーンに大きな変更を加える際は、IOG、カルダノ財団、EMURGOの3団体が所持するキーが必要となっており、ブロックチェーンのプロトコル変更を開始するトリガーは、この3団体の合意で行われています。3団体に分散しているものの、L1の開発においては、まだまだ分散化されたとは言い難い状況です。
今回の議題となっているCIP-1694では、この3団体が管理しているプロトコル変更に関するキーをカルダノコミュニティに手渡し、「真の分散化」を達成することが目標となっています。
「CIP-1694」とは、「カルダノをどのようにしてコミュニティ運営していくか?」という観点で執筆された改善案であり、いわば「カルダノの新しい運営方法」の設計図と言えます。
CIP-1694の仕組みって?
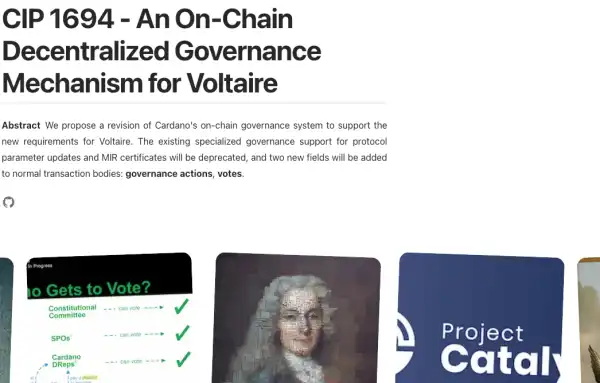
CIP-1694の案では、「流動民主主義(Liquid Democracy)」をベースとした民主主義体制で運営されることが想定されています。
ここではまず、CIP-1694での運営手順について簡単におさらいしましょう。
このCIP(カルダノ改善案)では、以下のようなフローでプロトコル変更が実施されることが想定されています。
①有志が、カルダノのプロトコル変更「案」を提案
②憲法委員会が、その案がルールに則っているかを判定
③変更案の投票を開始
④自分で投票、もしくはdRep(委任代表者)に投票。加えて、SPOが投票
⑤その結果で可否を決定
ADAホルダーの皆さんは、④のプロセスで、dRepやSPOに自分のステークを委任することで、間接的に投票に参加する仕組みとなっています。
CIP-1694時代には、特定の代表者して運営・管理するのではなく、「改善提案ごと」に投票が行われ、その都度、dRepやSPO、ホルダーが投票に参加する、というスタイルとなっています。
詳しくはこちら→
カルダノの「CIP-1694」とは? 解説記事を日本語で読む
カルダノのガバナンス、CIP-1694に向けて【全文翻訳】
CIP-1694の「流動民主主義」とは?
この「流動民主主義(Liquid Democracy)」は、実は独自のアイデアではなく、もともと政治における民主主義の改善案として研究されている考え方であり、CIPはこの考え方を採用したものです。
現在、日本ではほとんど語られていませんが、イエール大学の助教授として知られる成田悠輔氏がインタビューの中で紹介している記事などが見られます。(この記事では「液体民主主義」と訳されていますが、「そもそも液体ではない」「本質的は意思決定の流動性にある」「決まった訳語が定着していない」という理由で「流動民主主義」としています)
その歴史は意外と古く、1884年に『不思議の国のアリス』の作者として知られるルイス・キャロル(本名チャールズ・ドジソンとして発表)は、『議会代表の原理(The Principles of Parliamentary Representation)』の中で、「他動的投票」あるいは「流動的投票」という概念を発表したことが起源とされています。
では、CIP-1694をより深く理解するために、この考え方について簡単に押さえておきましょう。
まず民主主義システムについて簡単におさらいしましょう。
【直接民主主義 Direct Democracy】
民主主義の最も基本的なシステムで、全ての意思決定を多数決で決める方式。古代ギリシャなどで知られているものの、現代国家においては、無数の意思決定を常に投票で決めることは膨大な労力とコストがかかるため、規模の大きい組織には不向き。
【代議制民主主義 Delegative Democracy】
現在多くの国家で採用されているシステムで、グループの運営者を投票で決め、当選した者がグループを代表して組織運営する方式。
日本の衆議院選挙などでも、国民ではなく選挙で当選した国会議員が日本における意思決定者となっている。間接民主主義、もしくは委任制民主主義とも。
これに対して、流動民主主義は次のような仕組みです。
【流動民主主義 Liquid Democracy】
「直接投票」と「動的代表への投票」を組み合わせて意思決定を行うシステム。意思決定においては直接民主主義と同様に「各議題ごと」に投票を行う。投票の際は、自ら投票をする、もしくは「動的代表」へ投票することを選択できる。「動的代表」は委任代表者だが、委任民主主義とは異なり任期はなく、各議題ごとに行われる投票において、委任者に代わって投票を行う。
つまり、「CIP-1694は、流動民主主義をベースに、カルダノの特徴に合わせて調整したもの」と考えることができそうです。
代議制民主主義のデメリットとは?
前述の通り、直接民主主義(Direct Democracy)では、「意思決定に手間がかかる」「その議題に詳しくない一般人は、有効な意思決定ができない」という点があります。
その改善策として現在も多くの国で採用されている代議制民主主義(Delegative Democracy)では、「国会議員や大統領を投票で決める」仕組みです。数多くの意思決定を代表者が行うことで、選挙の手間やコストを削減することができます。
この仕組みは一見すると民主主義のように見えますが、「当選者が、常にグループの意志に沿って意思決定する保証はない」というリスクがあります。
20世紀初頭の政治学者ロバート・ミケルスは、1911年に著した著書『Political Parties(政党)』の中で、「ほとんどの代議制民主主義は、少数制支配や政党主義に向かって悪化する」と論じていたそうです。簡単に言えば、「少数のリーダーだけで政治が行われたり、一部の政党だけが権力を掌握する方向に向かう」ということです。
これは20世紀初頭にすでに指摘されていた問題点ですが、この一文だけですでに納得してしまう人も多いのではないでしょうか。
実際、代議制民主主義を採用した多くの国家で、このような問題に直面していると指摘ができます。
⚫︎アメリカ→共和党と民主党の二大政党が選挙によって入れ替わり、選挙によって政治的な立場が両極端となっている
⚫︎中国→共産党の一党独裁となっており、共産党に反対する勢力は処罰対象となり、実質的に民主主義が崩壊している
⚫︎日本→選挙で当選した岸田首相は、選挙中に掲げた公約を反故にし、全く正反対な政策を打ち出し大きな批判を受けるが、任期が継続しており解任させられない
このように、代議制民主主義は「誰がリーダーとなるか決める」という選挙ができるものの、決まったリーダーが国民が支持する行為を行うかは不透明です。
特に、多くの独裁国家では、選挙で大きく勝利した政党が法律を捻じ曲げ、自分たちへの反抗勢力を法的・政治的に排除するシステムを構築しようと目指す傾向があります。

このリスクの最たるものが、ナチスドイツです。独裁者として有名なアドルフ・ヒトラーも、第一次世界大戦の敗戦と世界恐慌によって低迷したドイツにおいて、圧倒的な得票数を得て一大政党となりました。その後の顛末は皆さんもご存知の通りですね。
ナチスは「選挙に大勝利した」ことを大義名分として反対勢力を苛烈に攻撃し、独裁政権の構築に成功しました。
つまり、代議制民主主義は常に独裁政治への危険をはらんでおり、バランスが崩れると民主主義が崩壊するという問題点があるのです。
流動民主主義のメリットとデメリットは?
このように代議制民主主義は、バランスが崩れることで民主主義が崩壊するリスクがあるというデメリットがあります。
流動民主主義は、このような代議制民主主義の問題を解消すべく考案された仕組みです。まずは、この流動民主主義のメリットから見ていきましょう。
①各議題(意思決定)の選挙で、常に投票者の意思が反映できる
流動民主主義では、直接民主主義のように「議題ごと(意思決定ごと)に選挙を行う」仕組みです。
投票者は「直接投票」も可能でありながら、「動的代表者を選ぶ」ことも選択でき、自分では判断が難しい議題でも委任者を選ぶことで有意義な投票が可能になります。
②動的代表者も各議題において審判が下る
動的代表者の任期は「その議題のみ」であり、その後に委任者の意思にそぐわない判断をした場合は、次の投票の際に別の動的代表者を選ぶことが可能です。これにより、動的代表者のスピード感のある不信任が可能になります。
このように流動民主主義では、代議制民主主義のデメリットであった「投票者の意思に反した決定」や「任期中の権力集中」を回避することが可能になります。
一方で、流動民主主義には次のようなデメリットも存在します。
①議題が多くなると処理しきれない?
「意思決定の煩雑さ」は、直接民主主義と同じデメリットです。直接民主主義と同様に、膨大な意思決定を選挙で行うことは組織のスピード感を下げてしまうため、組織運営が非効率的になってしまいます。
→この問題については、近年のIT技術を駆使することで可能という反論もあり、流動民主主義においてはほとんどの場合、インターネット投票を前提として議論が進んでいます。
しかし、インターネット投票を前提としても、次のような批判があります。これに対する反論と一緒に紹介します。
②情報強者しか参加できない?
インターネット投票では、IT知識のない人が参加できないため、多くの意見を収集することができない、という批判です。しかし、これについては、インターネット世代が主流となる将来においては解消される可能性もあります。
③専門的な知識のあるリーダーに任せた方が効率的?
専門的知識がない人が意思決定に参加することで、客観的に「正しくない判断」への投票が多くなるリスクが生じるという批判です。独裁政治においても、シンガポールやUAEなど成功している国もあるため、このような批判もあると思います。しかし、確率論的には独裁体制が成功する可能性は世界的に見ても低いことは明らかです。さらに、日本の代議制民主主義を見ても「専門性がない人も当選する」という事例は多数散見されており、流動民主主義特有のリスクとは言えないでしょう。かえって「専門性がある人物」が権力を集約するリスクを防げると考えることもできます。
④ITベースだと、ハッキングや改ざんのリスクがある?
ITベースの投票となると、やはりシステム障害やハッキングのリスクが付き纏います。特に問題なのが「誰がシステムを運営するのか」によって、運営勢力の思惑によって投票結果が操作されるおそれがあります。もちろん、反抗勢力によるハッキングでも同様のリスクが伴います。
2020年のアメリカ大統領選挙において、インターネット投票が採用されましたが、投票家かの不正疑惑などが巻き起こり大きな混乱のタネとなったことも記憶に新しいところです。
→「運営勢力による改ざん」については、完全に分散化されたネットワークであればリスク回避が可能です。次の「ハッキングリスク」については、ハッキングが極めて難しい仕組みを活用することが大切です。
分散化運営されハッキングに極めて強い仕組み…、つまり、ブロックチェーンによってこのリスクは解決できると思われます。
CIP-1694は「次世代の民主主義へのチャレンジ」である
ここまで情報を整理していくと、今回のカルダノの改善案「CIP-1694」において、流動民主主義システムが採用された理由も少しずつわかってきます。
①議題は「カルダノの運営」に限定されている
今回のCIP-1694では、カルダノのプロトコルアップデートに関する議題を議論・決定するものであり、議題となる項目は「カルダノ憲法」に則ったものに限定されています。有識者が論文を査読するなどのプロセスなども考慮されており、極めて重要な変更要件だけを投票で決めます。そのため、投票機会が多すぎるという心配はないと考えられます。
②情報強者じゃなくても参加できる
カルダノのCIP-1694ということで、やはり一般の方には壁があると考えられます。カルダノのプロトコルに関する議論のため、ここは情報強者だけが参加する、ということでもあまり問題ない、という意見もあると思います。
→しかし、カルダノを多くの人に利用してもらうためには、「判断の多様性」も必要です。あらゆる種類のニーズや意見が交わることで、今後100年続くためのプロトコル改善が可能になります。CIP-1694では、WebサイトやdAppsを活用したわかりやすいUIの提供に励んでおり、プログラミング未経験者でも参加が可能になる見込みです。
③専門家の改善案を投票で決める方式
CIP-1694においては、有識者が作成した「CIP(カルダノ改善案)」に対して、その是非を投票で決める方式です。CIPは有識者たちの審査や査読が入るため、素人の出鱈目な案については投票になる前に却下されます。
採用された議題は、発案者やその協力者たちの手で開発されるため、未経験者のCIPが採用されるリスクを低減しています。
④L1投票のため、ハッキング耐性や不正リスクは極小
CIP-1694は、カルダノのメインチェーン(L1)で行われる運営手段です。投票結果はブロックチェーンに刻まれるため公開されており、L1のハッキングについては、「やれるものならやってみろ」というレベルで堅牢さが証明されています。
そもそもハッキングが可能であれば、投票よりADA盗難した方がメリットが大きいでしょう…。
ちなみに、流動民主主義による意思決定プラットフォームの先駆者として「LiquidFeedback」という商業サービスがありますが、最新のver4.0ではこちらもブロックチェーン基盤となっているようです。
このように整理して考えると、カルダノの「真の分散化」を目指すプロセスとして「流動民主主義」を採用したことは極めて自然だったと言えるかもしれません。
透明性が高く、非常に堅牢なブロックチェーンがあるからこそ、流動民主主義の利点を生かすことが可能になると言えます。
むしろ「流動民主主義を成功させるために、カルダノを利用した」という、逆転の見方もできてしまうのではないでしょうか?
CIP-1694と流動民主主義のリスク
しかし、CIP-1694においても、流動民主主義における弱みを完全に克服できていない可能性も考慮する必要があります。
⚫︎一部の「有識者グループ」による階級主義が起きるリスク
まず懸念されるのが、議題の正当性を監視する「CIP編集者」と「カルダノ憲法委員会」の官僚的リスクです。CIP-1694においても、まず議題を投票という叩き台に出すための壁があり、これらが自分たちの思惑によって影響力を高めるようなことがあれば、運営におけるリスクとなる可能性があります。
これに対しては、「ADAホルダーは憲法委員会の不信任」を投票することで抑止力とする予定としています。
⚫︎人気者のdRepが得票を独り占めするリスク
憲法委員会などは、投票による抑止力が機能すれば問題なさそうですが、最も強く懸念されるべきなのが、「インフルエンサー的なdRep」による投票独占です。
カルダノの開発資金支援プロジェクト「カタリスト」でも散見されますが、ADAホルダーに特別な影響力をもつ人物がdRepとして参加することで、多くの得票を得て権力を行使する懸念です。
少数のインフルエンサーの思惑の利害に関係する議題に関する投票において、その影響力による投票操作の懸念があります。代議制民主主義においても「タレント議員」問題が常態化していますが、流動民主主義においても払拭が難しいと考えられます。
民主主義の最大リスクは「参加者」である
ここで、ナチスドイツに対抗したイギリスのウィンストン・チャーチル首相の言葉を紹介します。

democracy is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from time to time.…
——民主主義は、これまで試みられてきた他のすべての形態を除けば、最低の政治形態である……
これは私がイギリスの大学で国際政治を学んでいた時、政治学の講義で最初に教授に言われて衝撃を受けた、チャーチルの言葉です。
イギリスのジョークでは「下げて上げる」「上げて下げる」のが形式美となっており、普通に聞くと「最低だけど他にないよね」という自虐的なブリティッシュジョーク、という印象ではあります。
しかし、うがって解釈するなら「より良い民主主義の必要性」を訴えた苦言だったと考えることもできるでしょう。
現在の日本においても、自民党の支持率は20%台まで下落していながら、数年前の選挙で大きく勝利したことが原因で、今でも彼らを権力の座から引きずり下ろすことができません。その結果、その暴走を止めることができなくなっています。
アメリカにおいても、LGBTや窃盗問題、不当な暗号通貨弾圧など、通常であれば疑問に問われる法律が施行され多くの混乱が起きています。議会の多数派は共和党ですが、対立する民主党のバイデン大統領を失脚させるほどの議席数はなく、疑惑の行政が続いています(個人的見解です)。
現在、世界の多くの国で施行されている民主主義の制度では、一度選挙で勝利したリーダーによる「権力の暴走」を食い止めることは極めて難しいということができると思います。
そこで考案されたのが「流動民主主義(Liquid Democracy)」という考え方であり、ブロックチェーンは、この仕組みを現実化する必要案件だったと言うことができるかもしれません。
その一方で、「バイデンも自民党も、結局、選んだのは国民である」ことも否定し難い事実です。
代議制民主主義においても、国民の多数派が賢明であれば、現状のような混迷が起きる前に彼らの政権奪取を阻止できていたはずです。スキルのないタレント議員が当選するのは世界的にも珍しくはなく、流動民主主義においても払拭できない可能性があります。
分散化の基本は「trust no one (誰も信用するな)」
「CIP-1694」は、「次世代の民主主義」を実現するための社会実験として、非常に面白い試みだと思います。しかし、どのような仕組みであろうと、民主主義は人が主役であり、主役が人である限り常にミスが起きるリスクが伴います。
どのような民主主義体制であっても、人間の判断が最大のリスクである以上、常に自戒と監視が必要であることを肝に銘じておく必要があります。
つまり「流動民主主義は、代議制民主主義よりマシだが、やはり最低の政治形態である」という態度を忘れてはいけません。
暗号通貨において「trust no one(誰も信用するな)」が鉄則ですが、これは分散型投票でも同じです。
脳死で賛同するのでなく、「この仕組みに問題はないか」「より良い改善案はないだろうか」という批判的な態度こそ、カルダノを世界で最も分散化されたネットワークとして機能する最大要素であることを皆さんと共有し、本記事を終えたいと思います。
(了)
本稿はカルダノステークプール「CoffeePool☕️」が作成しました。
COFFEの活動を応援いただける方はぜひ、委任(デリゲート)のご検討をお願いいたします😊
TickerまたはPoolIDをクリック(タップ)するとコピーできます。
NAME:CoffeePool☕️
Ticker:COFFE
![]() [COFFE] CoffeePool️
[COFFE] CoffeePool️
pool1r55hyfrd3tw6nzpkvf4rfceh2f04yph92fc462phnd0akp2s5r6
pool1r55hyfrd3tw6nzpkvf4rfceh2f04yph92fc462phnd0akp2s5r6
NAME:CardanoKissa☕️
Ticker:KISSA
![]() [KISSA] CardanoKissa☕️
[KISSA] CardanoKissa☕️
pool1lugxr82p89qm35spzwccle405t5dfdznhrasyrtr2cyv2vyfud6
初心者でも長期ホルダーでも、楽しくカルダノ について語り合える discordスペースを作りました😊☕️
・なりすましやscam対策のためXアカウント認証で運営😊
・初心者ホルダーさん大歓迎!☕️
SPOも続々参加しています! ぜひお気軽にお立ち寄りください。
参加方法は☟
discord.gg/TNy7QNua7c